
井の中の蛙大海を知らず
私が小説を書き始めたのは、中学生の時。
当時の私は他人とのコミュニケーションが苦手で、いつも人の顔色ばかりを伺っては言いたいこと全てを紙に書き連ねていた。それも紙の上にただ言葉を書いていくのではなく、その中ではもう一人の自分がいて、代わりに相手へ意見を述べてくれる理想の姿を思い浮かべる。そんな想像でしか上手く立ち回れない、私が救われる為の物語を書いていた。
小説を書いていることを打ち明けたのは、昔から仲の良い幼なじみ。友達も多く、スポーツが好きなアウトドア派という私とは真逆の性格の子だったが、自身の意見をはっきり言ってくれる子である。
「読んで、添削してほしい」
感想を聞きたいからという理由で読んで欲しいなんて言えず、言い訳するように「添削」という名目でお願いした。
前述したように自己満足で書いているような私が、何故人に読んで欲しいと思ったのか。
今になって思い返してみたら単純なことで「自分ではない誰かに読んでもらい、凄く面白かったと言われたい」という欲が出たからだ。自分が満足するものなら、他の人が読んでも同じような感想を持ってもらえるだろうと自信があったこともあり、帰ってきたら「面白かった」と予想通りの結果になるものだと信じて疑わなかった。
「はい、読み終わったよ」
そう言って差し出された紙の束には、いくつもの攻撃的な赤色が入っていた。
もちろん、「面白かった」なんて感想もない。なぜなら自分が依頼したのは「添削」だから。
返ってくるのは文章の違和感のある部分を指摘されたもので、学校のテスト用紙のようにチェックマークはないものの赤く記された文字が、高く伸ばしていた私の鼻を容赦なく折っていった。
普段から、周囲の目を気にして良い子供として徹してきた。
大人から注意されることを恐れ、間違いをしないようにしてきた自分にとって
その赤い文字で、初めて自分の未熟さを自覚させられた。
そして同時に私の中に芽生えたのは、悲しみでも怒りでも、ましてや諦めでもない。
『悔しい』 という気持ち。
あぁ、こんなミスをしているなんて。
もっと違う表現方法にするだけで、より良いものになっていたはずなのに。
これが出来ていたなら違う感想を得られたかもしれない。
「井の中の蛙大海を知らず」とは、このことだと思い知った瞬間だった。
この日を境に、私にとって小説を書くことが
「自分だけが楽しければいい」ではなく、「誰かに楽しんでもらいたい」に変わっていく。
今はまだ万人に受け入れられるようなものではないけれど
書き続けて、誰かに読んでもらって、いつか誰かの心に残る物語を作りたい。

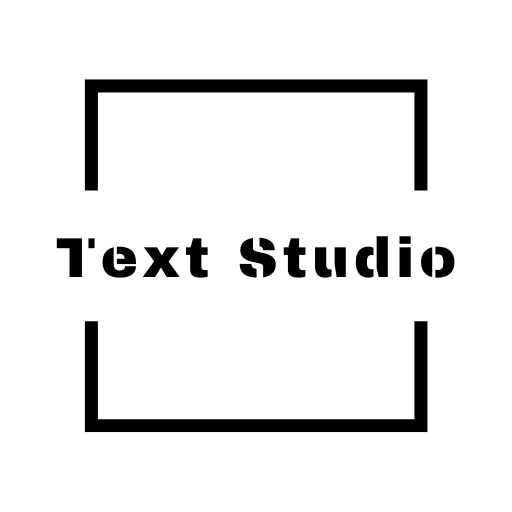






コメント