
よういちろう
コーヒーが嫌いだ。飲み物に似つかわしくない黒色と、苦さに混じる香ばしさが嫌いだ。馬鹿にされているような気さえする。そう私が言うと大和くんはいつも、子供舌だなあと笑った。
「飛行機が遅延って、電車みたいだね」
「まあいいじゃん、朝飯食う時間できたし」
大和くんはサンドイッチとミルクレープとコーヒーを注文する。先に野菜がたくさん入ったサンドイッチが届けられたので、大和くんはそれを味わっているのかどうか分からないような食べ方で食べた。大和くんは美味しいものを食べるととても満足そうに頷く。やはり味わっているのかもしれない。私はそれを見ながら唯一注文した紅茶を一口飲んだ。このお店は紅茶もコーヒーもたくさん種類がある。紅茶は茶葉の種類でダージリンやアッサムやセイロン、フレーバーティーのアールグレイを揃えていて、レモンティーやミルクティーも客が好みの茶葉を選んで注文することが出来た。私はダージリンのセカンドフラッシュをストレートで注文した。夏摘みの茶葉の軽やかですっきりとしたフルーツのような味わい口の中に広がる。大和くんはコーヒーをホットで注文する。豆の種類ごとにたくさんの種類があるけれど、大和くんはコーヒーとだけ告げて注文した。初めて来たお店なら、一番飾ってない味がいい、なんて言うところがとても彼らしいと思う。
「ミルクレープにはコーヒーと紅茶、どっちが合うと思う?」
「比べるものでもないでしょ」
私がそういうと、大和くんは、確かにと言って納得した。大和くんがサンドイッチを食べ終えたタイミングで店主が大和くんのコーヒーを淹れ始める。店主が淹れようとしているのはコロンビアの深煎りのもので、コーヒー豆の減り具合から見るにこの店で最も売れているようだった。大和くんは鞄からスマートフォンを取り出して画面を確認する。飛行機は霧の影響で予定よりも少し遅れているらしい。まるで他人事のように大和くんはそう言った。
「茉優さんは朝飯食わないの?」
「食べない。ていうか朝は喉通んないから」
「朝は食った方がいいよ。一日が全然違うもん」
「年下の癖に」
私は紅茶をもう一口飲んだ。まだ温かみ残している。透き通ったオレンジ色は如何にも上質な飲み物のそれをしている。大和くんは白いTシャツ一枚に下はジーンズを履いている。まるで一人夏を先取りしているような格好だ。私はブラウスの上に一枚簡単な羽織ものを着ている。夏が近づいてきたとはいえ、この時間はまだこの世界の暑さとは切り離されている。
店主がミルクレープとコーヒーをテーブルに届けてくれた。小さめのミルクレープには薄く切られた苺が挟まっている他には生クリームが層をなしているだけのシンプルなものだった。大和くんは先にミルクレープを一口食べた。また納得するように頷くと、私にも一口食べるように促した。苺の甘酸っぱさ、生クリームの滑らかさ、生地のおっとりとした柔らかさ。甘すぎない味がとても心地が良かった。
「おいしい」
「問題はコーヒーに合うかどうか、だね」
大和くんはコーヒーを一口飲む。彼の表情を見ればそのコーヒーがミルクレープと良く合うのが一目で分かった。私も紅茶を一口飲む。甘すぎないミルクレープと、癖のないダージリンが良く合った。きっとこちらも、負けないくらい美味しいと思う。私と大和くんとは、好きなものや関心を持つものやこれまでの人生で影響を受けてきたものがそんなに似ていないと思う。私は朝食は食べたくないけれど、大和くんは必ず食べる。私は高い料理や有名なお店に行ってもあまりおいしく感じないものがあるとすぐに顔に出てしまうけれど、大和くんは味や食感に敏感な癖に、ファストフードや加工食品や冷凍食品も好んでよく食べた。大和くんは嫌いな食べ物がない。大和くんは食べ物が好きで、食べることが好きで、料理も好きで、食事を提供する場が好きで、食を支えるインフラストラクチャーが好きだ。大和くんのそう言うところが、私は好きだった。
コーヒーとミルクレープはあっという間に減っていったけれど、大和くんが乗る予定の飛行機は運転再開までもう少し時間がかかるようだった。大和くんはこれから飛行機に乗ってフランスのパリに行って、知り合いの働いているホテルのレストランで見習いとして働き始める。私は何年たっても景色の変わらない東京の風景の一部として、明日からまた働き続けるだけだ。私と大和くんが出会ったのは恵比寿の小さなバーで、もう三年も前の事だった。大和くんは当時まだそのバーでアルバイトをしていて、私は当時付き合っていた男に裏切られ小説のヒロインのように傷心していた。それから大和くんとは何度も連絡を取ったり、食事や少し遠くに出かけたりした。私と大和くんは、世間的には友人と言って間違いない。大和くんの事が好きだがそれは恋愛的な感情というよりは親しみと敬いに近いような気がした。大和くんは出会った頃から、いつかフランスで自分の店を持ちたいと話していた。彼は自分の夢を、如何にも現実的に検討しながら話す。夢を語っている自分に酔うのではなく、その一言一言に責任感を感じながら語っていた。そういう彼の強さに、私はこの三年間支えられていたのだと思う。
「もう一杯コーヒー飲もうかな。茉優さんは?」
「私はいいや」
大和くんはもう一度店主にコーヒーを注文した。注文の方法はあいかわらず、コーヒー、と告げただけだ。大和くんと私の目が合った。大和くんの目は真っ黒にほど近い如何にも日本人的な茶色をしている。大和という名前もとても日本人らしいし、体型や顔も日本人らしい。何よりも大和くんは一度志したものを曲げないような、芯の強さを持っている。それがまた、何とも武士のような律義さだった。私にもほんの少しだけ彼の芯の強さがあったとしたら、彼のような意志の強さがあったとしたら、今私はもう少し背筋を伸ばして座っている事だろう。だけど、無いものをねだることほど、自分を惨めに感じることはない。
店主が大和くんの二杯目のコーヒーを淹れ始める。私は、店主がどの豆を選んだのか見逃してしまった、と思った。先ほどと同じコロンビアの深煎りのものかもしれないし、中煎りのものかもしれない。その隣に置かれているグアテマラや、そのまた隣にあるキリマンジャロかもしれない。たったそれだけ、知っていなくても知らなくても誰も困らないようなそれだけで、私は途端に、大和くんとはもう会えなくなるのだと実感した。あとほんのわずかな時間で、私は最愛の友人を失って、この孤独な東京に独りぼっちになるのだろう。
私がもし大和くんと付き合っていたら、大和くんの恋人だったとしたら、この別れに涙を流す権利があったのだろうか。夢に向かって進もうとしている彼に対して、意見をする権利があったのだろうか。私を置いていかないでくれと、叫び出してしまう権利さえ、私にはないのかもしれない。次第に私の方までコーヒーの香りが届く。大和くんはもう一度スマートフォンを見た後、少しだけ私に寄り添うような目で、私を見た。
「飛行機、動き始めた。もう行かないと」
「まあコーヒーくらい飲んでいきなよ」
「茉優さんにあげるよ」
「コーヒー飲めないもん」
届けられた二杯目のコーヒーは真っ黒だった。黒い水面がゆらゆらと揺れている。水面に顔を落としてる私の表情が映った。コーヒーの苦くて香ばしくて、私に優しくないところが大嫌いだ。
「行くの止めちゃいなよ。料理なんて東京でいくらでも出来るじゃん」
「まあそうだね」
「フランス料理のお店だっていっぱい美味しいとこあるじゃん」
「うん、確かに」
「ほら、じゃあ」
「まあでも、これは俺が決めたことだから」
私は顔を上げた。大和くんは笑っている。優しい大和くんなんて、嫌いだ。
「私を置いてかないでよ」
「大丈夫だよ。もう。茉優さんは」
大和くんは一口だけコーヒーに口を付けた。大和くんにはコーヒーの豆の種類が分かっただろうか。きっと大和くんなら分かったと思う。大和くんは私の事も良く分かってくれている。大和くんと一緒に居ると甘えてしまう事も。もう私も立ち直って生きていかなければならないことも。大和くんは私の背中を押すように別れを告げた。
「いつかまた会いましょう。その時は、ご馳走するよ」
大和くんは大きなバックパックを背負って、店を出て行った。
お店に残されたのは、まだ湯気が立っているコーヒーが一杯と、私ひとりだった。コーヒーの黒色は、よく見ると少しだけ茶色がかっている。つやつやとした色に混じって、泣きそうな顔の私の顔が映っている。
私はコーヒーを一口、口に含んだ。口の中に苦さが広がっていく。この世界の他の何にも似ていないその苦さが私の中に充満していく。
コーヒーと紅茶、どちらの方がミルクレープに合うのだろう。どちらもミルクレープに必要な味わいなのかもしれない。
大和くんと過ごした私の三年間が、未来の私にとって必要な時間だったと信じたい。
大和くんの決心が、彼の夢に繋がっていることを心から祈っている。
だけどコーヒーはまだ、私には少し、苦すぎたみたいだ。

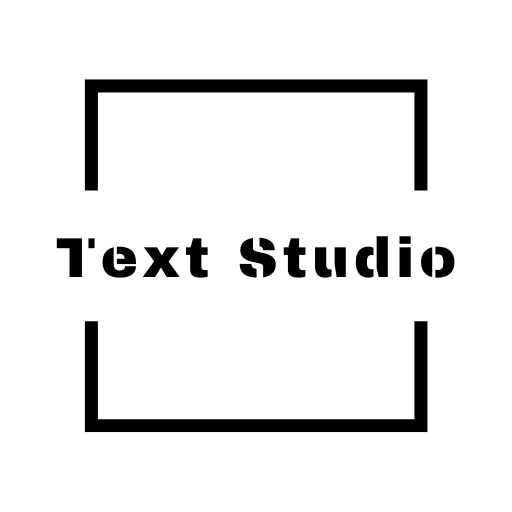






コメント