
母は春の海に還った。
代わりにかんざしとサンダルの左半分、そして彼女がお気に入りでよく着ていた着物の帯だけが泥水の中から見つかった。
かんざしとサンダルは葬式で母の代わりに焚べられたが、父はその帯だけは手元に残した。光沢のある臙脂の生地に桜の刺繍が縫い付けられている。それは幼い私と未熟な父を、文字通り、縛り付けるようだった。
*
一日四時間のレッスンを週五回。実技試験を前に、先生は私よりも熱が入る。入試の自由曲にはドヴォルザークを選んだ。母との思い出についての曲とは、我ながら洒落が効いていて気に入っている。
先生は耽美な言葉で私を褒めた。私に才能があると信じて止まない。それは無責任なことだ。母のようにピアノを弾いて食べていける人間が世界に何人いるのだろう。それを知りながら彼女の背中を追う私のことを、母が生きていたらどう思うだろう。あなたには無理よ、と軽く笑ってくれるだろうか。
母の死後、父は勤め先を辞めて帰国した。私よりよっぽど精神的に堪えたらしく、しばらくは定職にもつけなかった。それでも時間は絶えず過ぎる。地元の企業に再就職して早五年、ついに父も腹を括ったらしい。
「母さんの帯な、このままにするのは申し訳なくて。それに、どこにも行けん気がするからさ」
知人に預けて別のものに仕立て直そう。それは父なりの、再起に向けた決意なのだと思う。
合格通知が届いたのは、母と、そのほか多くの人の命日だった。
海辺には多くの献花が供えられている。午後二時四十六分、水平線に向かって一分間の黙祷を捧げた。この春から私は、母と同じ学校に通うことになる。
死んだ人間は生きている人間よりも強いのだろうか。あの脆弱な春からずっと、私と父は水の中をもがくように生きている。海に還った母だけが、私たちのすべてを知っているのかもしれない。
黙祷を終えると、靴を脱いで海に向かって歩を進めた。裸足で三月の波を踏みしめ、そのまま膝まで水に浸かった。冷たさの中に、確かに温もりを感じる。そして、重力に従うように、背中から体を海の中に沈めた。
勢いよく両耳に入った水が、ごうごうと音を鳴らし始める。それはまるで、母が私に音楽を教えているようだった。その深い音を聴きながら私は、まだ母のお腹の中にいる自分を想像した。泣き出してしまうのは、すんでのところで我慢した。
無論、体調を崩したので、合格祝いは数日後に催された。父からプレゼントされた鍵盤カバーには、母の帯と同じ生地があしらわれている。
「合格おめでとう」
父の言葉に、母の声が重なって聞こえた気がした。
私はそれを受け取ると鍵盤に被せるように置いた。臙脂の上に輝く桜に、そっと指先で触れた。
私はこれから、母と同じ道を歩むこともできる。もしくは母の背中にも父の期待にも縛られず、思うままに生きることもできる。強靭な自由を突き付けられた私のもとに、間もなく、また新しい春がやってくる。




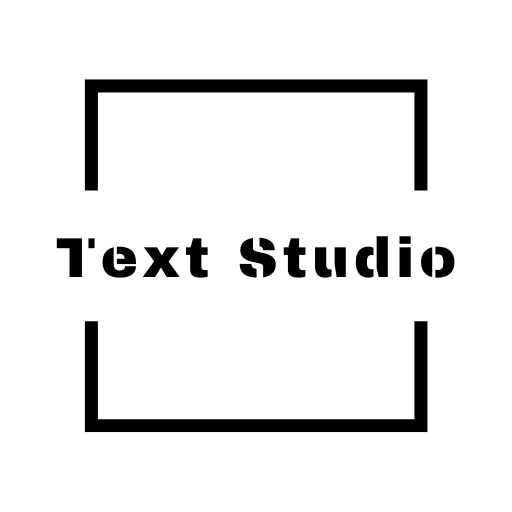


コメント