
私が最初に打ち明けたのは、小説を書いていることではなく“小説を書きたいこと”だった。
「お母さん。小説書いて応募したいんやけど誰かパソコン譲ってくれへんかな」
高校2年生、ちょうど進路希望調査票が配られた春のことだ。
当時の私は家計を詳しく理解していたわけではないが、パソコンを“買ってくれ”とは言えない環境であることは察しがついていた。
"譲ってくれる人を探してくれ”であればまだ実現が可能な話として聞き届けてくれるかもしれないと踏んで、私はキッチンに立つ母の背中にそう声をかけた。
「ええよ。あんた、遂に読むだけじゃ足りひんなったみたいやな」
天ぷらを揚げているせいで完全には目を離せないのか、顔だけで振り返ってにやりと笑い母はそう言った。
後から聞いた話だが、母も子供の頃は女優か漫画家を志していたそうだ。
結局、時代柄『長男が大学に行っていないのに女を自由にさせるわけにはいかない』という風潮に飲まれ、彼女は挑戦すらさせて貰えずに私の母となる人生を歩いてきたらしい。
「我が子なら、いつかそういう日が来ると思ってた。買ってあげられへんのは申し訳ないが任せとけ」
母は私のお願いから2日でパソコンを調達してきた。遠方に住む叔母が古いノートパソコンを初期化してすぐに送ってくれたのだ。
同級生はみんな家にデスクトップパソコンを持っているような時代だったので誰にも自慢は出来なかったが、それは私にとって最高の宝物になった。
私は人差し指のぽちぽちタイピングから執筆を始め、2か月かけて処女作を完成させた。
その頃にはもう親戚連中に執筆について触れ回っていたし、近しい友人にも伝えていた。
私にとって、小説を書いていると打ち明けることは最初から秘めるようなことではなかったのだ。
【ちなみに余談】
私の処女作は小さなコンペで入選した。
それをきっかけに私は進路希望を芸術大学にしたため、教師陣に私の小説家志望が知れ渡った。
そしてAO入試で学内最速の合格を決めたことが噂になり、同級生にも小説家志望が筒抜けになった。
トドメに司書教諭が図書だよりに私の作品の冒頭を掲載したことで、保護者にまで広まった。
驚くほどに鮮烈なプチデビューになったことを、私は忘れない。
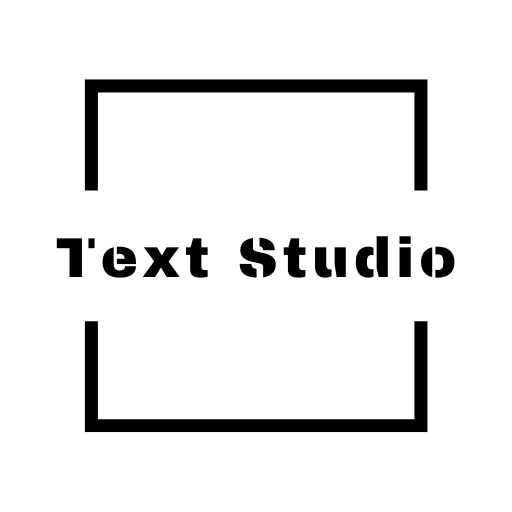







コメント
一箇所だけ俺を使ってるところに、強い喜びを感じました。
@はのうぃん
あぶねぇ! 自我が出てた! 教えて頂きありがとうございます!!