
ちせみくに
街灯に照らされる、私はちょっと、夜光虫。光の差さぬ、夜の端。私は一人、お散歩に伺います。からから鳴った足音が、すっと耳に抜けて心地いい。車は無い。人も通らない。勿論、一番惨たらしい自転車も姿を現さぬ。夏は夜。清少納言は素敵。良い目を持っていると思う。夜風を探して、こっそり家を抜け出すもをかし。
右側のポケットには小さなお財布をひっそり忍ばす。牡丹の刺繍が厭らしくない。中にはたぶん、五百円玉が三枚と、五円玉が二枚。五百円玉は潔い。思ったよりも買えないものがいっぱいあるけど、何も買えないと嘆くほど安くない。私みたいな可愛い奴だ。左のポケットから煙草を一本取り出します。
宵闇に 煙の香る 蛍火か
星が綺麗に見える。なんて語るほどには美しくない、この街の景色が好きです。コンビニエンスストアまで気が遠くなるほど歩いて、ヨーグルトと林檎ジュースを手に取って散々迷った挙句、牛乳だけを手に取って帰る。これが一番おいしいと感じる私を、私はちょっと大事にしたい。牛乳の、あの何とも言えない田舎者らしさが私を私たらしめるのだ。体の中に染み入る、あの何とも言えない香りには、誰か名前を付けてくれないものだろうか。その名前を付けた人と私は将来結婚しよう。でもそう言う人はもしかしたら、歩きながら煙草を吸う私を好きにはならないだろうと思う。拝啓、少し未来の私よ、煙草は今すぐ止めた方が良い。追伸、煙草は二十二時が美味い。
この街は小さな道で入り組んでいる。刺繍のような街である。夜道を縫うように歩いている。出来れば今日くらいは、誰にも見つからないままこの小さな旅を終えたいものである。陽の落ちた道なりには青白い街灯がぽつり、ぽつりと灯っている。風が少しだけ吹いていて、その音は細やかなのだけれども、私の熱を持った頬を大人気もなく撫でて去って行くのだ。独り占めしてしまいたくなるような清々しさに、思わず一人、微笑む。
街灯に 夜ぶりし我と 夜光虫
目を瞑って、この道がどこへ続いているのか想像してみる。牛蛙の眠る小川。蛍の鳴く林道。月の微笑む丘。目を開ければそこには何一つない、ささやかな小道が遥か先にあるコンビニエンスストアまで延びている。薄っすらとした涼しげな風が私の髪に触れては、軽やかな足取りで追い抜いて行った。
この風景を私は、いつまで鮮明に記憶に残しておくことが出来るであろうか。明日の私が、今日の私と同じ人間とは限らない。この煙草は、明日には灰になっているのだ。私の耳に残っている静けさは、今の私が独り占めしている。それはとても嬉しいことで、と同時にとても切なくも感じる。
コンビニエンスストアの光は、夜光虫よりも少し小賢しい。私のような正直者を罠に掛けようとしているのだろうと思う。大人しく罠に掛かれば良いものを、私は店の外の灰皿で煙草の光を揉み消した。
「みっちゃん」
ヨーグルトと林檎ジュースで迷っていると、さっちゃんが私に声を掛ける。夜に人と会うのは、幾つになっても少し照れ臭くて、少しだけ悪いことをしている気分になる。けれどそういう悪さが時に、私を大人にしてくれたのかもしれない。
「明日、早いんやないの?」
「早いもんかい。いつの夜かて、起きたら朝や」
「たまにはこっち帰って来てな」
さっちゃんはちゃきっと手を振って去って行った。私は悩んだ挙句、牛乳を買って帰る。牛乳は明日も同じ味だろうか。まさかこの田舎者に限って、裏切るようなことはするまい。コンビニエンスストアの光はやはり眩しすぎて、目がちかちかする。
夜を食み 白靴に飛ぶ 泣き虫や
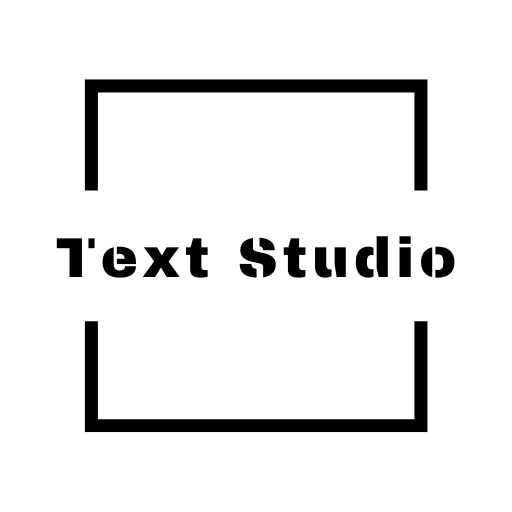

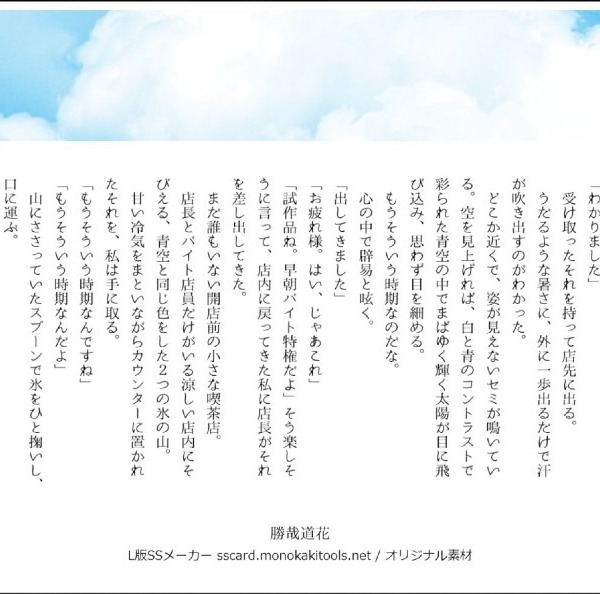



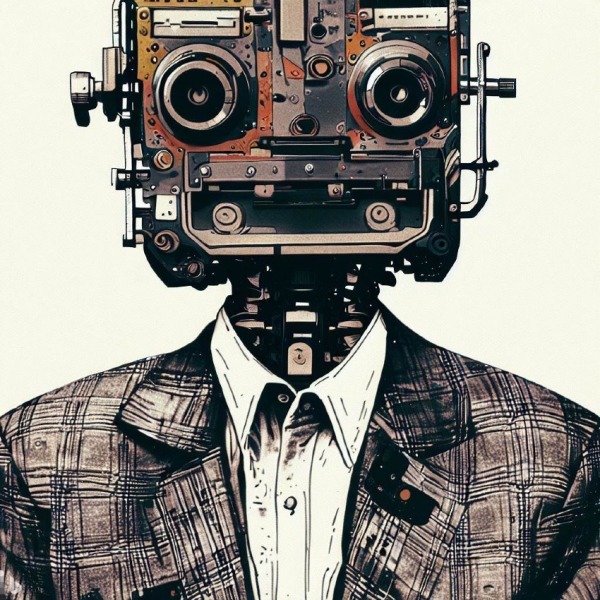

コメント