
2つの花束
人は何歳まで記念日を覚えているのだろう。記憶できるのはいくつの記念日なのだろうか? 出勤する前にそんなことを思いながら洗面台の鏡で自分の顔を見た。ファンデーションを塗る前の肌は艶がなくなって目だって腫れぼったい。
祖母のいる九州に住んでいる母は
「いつまでも過去のことに縛られなくても、そろそろ紗良も幸せになっても許されるんじゃない? 」
呑気に何もなかったように電話口で言ってきた。
許される? 死人に口なし。許されるわけがない。一度は私が殺しかけたようなもの。殺人未遂で逮捕されてもいいぐらいなのに。誰の名言だったか、歳を取ると全ては表情に出ると読んだことがある。今の私は醜いだけだ。
最低限、生きてゆけたらいい。製菓工場の箱詰めの仕事もベテランの域になっていて今、一番の願いは会社が倒産しないことだった。
仕事を終えて作業着からワンピースに着替えたあと、花屋へと急いだ。途中、横断歩道で立ち止まって街頭テレビを見上げた。ニュースは当事者の家族以外、あっと言う間に過去になる。あの日、画面に映った彼と彼女の名前、そして顔写真。殺虫剤のコマーシャルが流れているのに私の目にはもう一つ、あの日の画面が映っていた。確か、あの日、ここで同じように画面を見上げていた彼女はあれから元気だろうか?
花を買って生けたからって償えるわけじゃない。そもそも生きてる私には死後の世界なんてわからない。それでもその日がくるたび花を買って二人のために生けることぐらいしか私には償うことが浮かばなかった。いっそ──と思った瞬間、あの傷つけた日の彼の姿と血の匂いが浮かんできた。
18時55分、閉店まではあと5分、私は店先に並べた観葉植物を店内に片付けようとしていた店主に声をかけた。
「まだ、大丈夫ですか? 」
「こんばんわ。はい、大丈夫です。もしかして、トルコキキョウですか? 」
「えっ? はい。覚えてくれてるんですね」
「毎年、6月15日とお盆、お正月前になるとトルコキキョウの花束を買いに来られてますよね? 6月15日今日は大切な人の誕生日なのかな? そんなふうに誰かに花束をプレゼントしてもらえる人は幸せだなって思ってました」
店主はそう言うとショーケースの中からクリーム色のトルコキキョウの花を取り出して
「このくらいでいいですか? 」
と片手で握れるぐらいの束を見せながら私に聞いてきた。
「はい、お願いします」
大切な人の誕生日ではなく命日だった。夏の終わりの恋だった。恋というには相手を追い込んで苦しめただけの、『若気の至りで……』とは簡単に口にできるようなことではなかった。私は命日になるとこの店に来てトルコキキョウの花束をオーダーした。花と話すように葉のひとつひとつが痛まないように服を着せるように花束にする店主の指の動きを見るのが好きだった。
「出来ました。はい、どうぞ。喜んでもらえると僕も嬉しいです」
「ありがとうございます」
毎年、それで会話は終わっていたのに、その日、私は3000円手渡したあとで「命日なんです」
余計なことを言ってしまった。
「命日ですか? 」
「はい、傷つけた人の命日なんです。どう謝っても許してもらえないようなことをしたんです」
「そうなんですね」
それ以上の会話はなかった。
「ありがとうございます、余計なことを言ってしまいました」
「あの、もう僕も仕事終わりなんてよかったら聞きますよ、珈琲飲みますか? 」
店主はバックヤードから椅子を持ち出してきた。
「何か少しそわそわします。森にいるのとも違うし、でも生きてるんでしょうね、なんだか見られてる視線を感じます」
「僕にとっては、そうだな、なんだろう? 友達でも仲間でもないけど、エネルギーをもらってるソーラーパネルみたいな感じですかね? 仕入れてきて、ほんの一瞬だけここで共に時間を過ごして、誰かのもとで可愛がってもらえるようにおくりだす。時には誰かの命と一緒に燃えるために送りだすこともありますけど」
「そんなふうに考えたことはなかったです」
「少し待ってくださいね。珈琲いれてきますから、遠慮なく腰掛けてください」
私は手に持っていた花束を再びカウンターに置いて腰掛けた。
「お待たせしました。ミルクはないですけど、どうぞ」
「なんだか、へんな気がしますけど、いただきます」
「いつもね、思ってたんです。トルコキキョウばかり買われてるから、永遠に思える誰かがいらっしゃるのかな、って」
「永遠というより、一番大切な人が大切に思ってる人から私は奪おうとして自殺未遂をさせるほど追い込んで……結果、二度と会えない形になりました。自業自得というか、いつかもっと大人になったとき、謝りたいと思ってたんです。その人にも相手の方にも。でもそれは叶わない願いになりました。ふたりとも土砂崩れで亡くなったんです」
「そうでしたか……、僕は何一つ知らないので何も言えませんが、とどいてるんじゃないでしょうか? あなたの苦しみもきっと」
「私は九州に引っ越して結婚したことにしてました。二度と彼が私のところへ来ないように、と。私も彼のところへ戻れないように、と。でも本当は九州になんて引っ越してもないし、彼と別れたというか、ほんの数日、一緒に暮らしたあとは誰とも付き合ってません。それまでが嘘みたいに」
珈琲カップに口をつけながら、淡々と話す私の言葉を店主も淡々と聞いていた。
「そうだ、あなたと同じようにね、やっぱり6月15日になるとかすみ草だけの花束を毎年買いに来られる方がいるんです。年配の、だけど綺麗な方でその方も同じように娘さんに謝りたかったけどそれが叶わぬ願いになってしまったと話されてました。花を求める人の気持ちも様々なんですよね」
「本当に──。でもありがとうございます。誰にも話せない話だったんでほんの少しだけ軽くなりました」
私はそう言ってカウンターに置いてある花束をとろうと立ち上がった。
「上書きできますか? 」
「えっ? 」
「その人を僕で削除することはできますか? 」
私はリストバンドを外して傷だらけの手首を見せた。
「あなたが思ってるようなそんな素敵な人間ではないんです。私は、少なくとも大事な人に『死んでくれ』と許されないことをしたんですから」
「そんなにきれいに生きてる人ってどれだけいますかね? きれいに生きてるつもりでも心の中なんてわからないものですよ」
「びっくりしないんですか? 」
「しませんよ。そんなことぐらいでは。逆にその影に惹かれたんだと思っています。そろそろ、自分のために自分の好きな花を選んでもいいんだと思います」
涙は出なかった。ずっと前に誰かにそんなことを言ってほしかった気がする。その誰かは紛れもなく良太さんだった。
「ありがとうございます。こうして話せてよかった、んだと思います」
私は今度こそ、花束を手に持って店の外に出た。
商店街の他の店からシャッターが降りる音がして後ろからはドアの鍵を閉める音がした。
『二度とこのドアをノックするな!! 』
病室のドアの向こうで良太さんのお父さんから怒鳴られた声、その声の向こうに良太さんの声が聞こえた。
『親父、紗良さんのことを悪く言わんといてくれ!! 』それが最後の声だった。
部屋に戻ってテーブルの真ん中に飾るトルコキキョウ。
もし、あのときに……、戻ったとしても私は多分、同じように良太さんに惹かれて節子さんから引き離そうとした。多分、何度だって、この結末がわかったとしても。
「どうして他人のものを欲しがるの!! 」
「お母さん、他人のものだからほしいんだよ。幸せそうに見えるからそれがほしかったんだよ」
私は泣きもせずそう言い返して母を呆れさせた。昔からそう、私は他人の幸せがほしかった。私の中は空っぽだと思っていたから。ふと見上げた夜空に月は見えなかった。その代わりに目の前に突然、花束が見えた。
「あのう、これ」
花屋の店主だった。
「なんですか? 」
「プレゼントです。芍薬とユーカリ」
「……」
私は驚いて声が出なかった。
「さっき珈琲淹れるとき、実はバックヤードで作ってたんです。ずっとね、気になってたんです。一目惚れかもしれません。でも簡単じゃないから、ずっと言えませんでした。歩きましょうか── 」
手は繋がなかった。でも名前も知らない店主は私の隣を歩いた、花束を持って。
「ごめんなさい。迷惑じゃなかったら、あなたの名前を教えてもらえますか? 」
「紗良です。悪い子だからかな、さらの『ら』は良いって字です」
「僕の名前は『水』って書いて『すい』って言うんですよ、なんか芸名みたいでしょ? 」
「本当ですね、なんか名前負けしそうな名前です」
話しながら歩きながら、どこまで行くんだろうか? と思った、私も水さんも花束を手にしたままで。
どこかで良太さんが、いや節子さんが見ているとしたら私は許してもらえるだろうか?
「紗良さん、知ってますか? トルコキキョウのもう一つの花言葉は『良い語らい』ですよ」
不思議な人だと思った。私をどこに流したいのだろう? 私とどこに流れたいのだろう?
夜の海がタールのように怖く見えるように夜の川も昼間とは何一つ変わらない水の流れなのに光の加減で吸い込まれていきそうな強さがあった。道路を走る車の走行音と足音だけが二人の間に響いていた。
「実は──、辞めるんです。今月いっぱいでお店を。正確に言えば花屋はそのまま別のオーナーになって継続されるんですけど、僕はここから離れる」
「離れる? 」
「少し旅をしてみようかと思っていたんです。あなたと、いや紗良さんとこんなふうに話せるとも思って見なかったから」
「水(すい)っていう名前は流れてゆくことですもんね。自由でいいなぁと思います」
手にしていた2つの花束が一気にずしりと重みを増した。
ほっといてくれたらよかったのに──、どうせ消えてしまうんならこんな時間なんかいらなかった。一瞬、そう思って。
「でも、そんなんだったら無視しといてくれればよかったのに、この時間のこの想い出も私にはいらない」
人前で感情を見せるのは久しぶりだった。私は向きを変えた。
そういう意味ではないとか、待ってとか、追っかけてくると思っていたら水さんは足をとめなかった。
私は川沿いから大通りへと出た。これも天罰なのかもしれない。私はこうやってこれからも自分に起こる不幸の一つ一つに意味を持たせて納得させてどんどんと色褪せてゆくんだ。
雨は降ってなかったのに街路樹から雨の匂いがした。通りすがりの車も反対側を歩いているスーツ姿のサラリーマンも何を目指して明日への糧にしてるのだろう? それともあの頃の私みたいに何も考えずに自分の欲しいものを自分の手の中にただただ握っておきたかっただけなのだろうか? 月はそこにあっても誰も照らしはしない。月と地球の狭間にあるもの──、
『ハアッ ハアッ ハアッ ハアッ。こんなに……走ったのは……久しぶり……で…… 』
水さんだった。
私は無言のまま、そのまま歩いた。
よほど全力で走ったのか、水さんの『ハアッ ハアッ』という息が耳に響いてまるで変質者につけられてるみたいだと思ったら、私は『プッ』とおならが出たみたいに笑いが出た。
「紗良さん? 」
「ごめんなさい。なんか……息づかいが変質者につけられてるみたいで……」
「変質者? 僕が? 変質者ですか? 」
水さんはムッとした。その後で
「紗良さん」
私の手から花束を奪って右手で私の左手を握ってきた。そして言ったんだ。
「命日からはじめてみませんか? 本当に不謹慎だけど命日だからもしかしたら彼が出会わせてくれたと思い込んで──」
2つの花束の重みが手から離れた瞬間、どこかでほっとした。
月を見上げてもかすかに見える星を見てもただそこにあるだけで誰の味方でもなかった。それでも
「お腹がすきました。晩御飯!! 」
私は水さんの手を振りほどくことなく、目の前に見えていたラーメン屋を右手で指さした。
「じゃあ、とりあえず、ラーメン行きますか!! 」
花屋であることと、もうすぐそれを辞めること、名前が水であること、それだけしか知らなかった。
それでもきっと水さんもはじめたかったのだろう。
きっと傷つけて傷つけられても、『恋』というものを。
命日の夜だった。
過去に遡れば、彼が亡くなった夜だった。
「生きている僕らにはどうやったって死ぬことはわからない。だから生きている僕らには生きるしかない、生かすしかない花を生けるように」
隣の席からにんにくと芋焼酎のなんともいえないもさっとした匂いがする中で花束を2つ丸い椅子に置いたまま、水さんはそう言った。




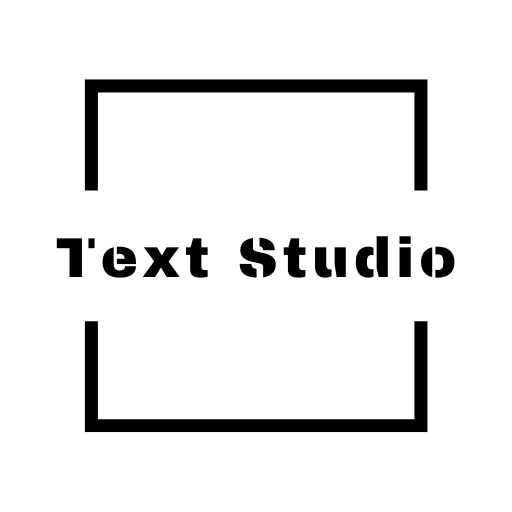



コメント