
妹の三回忌はあっという間(本当は長いと思われる)に終わった。喪服を脱ぐと、隣で香さんが心配そうな目で私を見る。「ご飯、食べれてます?」私はもちろんよ、と軽い笑みで返した。
働いていた頃はもう少し筋肉があったんだけれど。一日中子どもの世話をしていた保育士の仕事は、妹が脳梗塞で倒れたのを機に辞めた。彼女の左半身に麻痺が残り介護が必要になったからだ。妹はその状態で二年間生きて、そして二年前に亡くなった。
息子が車を出してくれるというので、香さんと三人で食事に向かうことにした。「介護の助けになりたい」と言って免許を取った息子の運転は、以前よりも随分と上達したようだ。後部座席からの風景は、その一つ一つがいつもよりずっと鮮明に目に留まった。あそこの回転ずしの店員さんは、三人がかりで車いすを持ち上げてくれたな。あっちのファミレスでは妹が苦手なはずのトマトのパスタを注文した。倒れた後の妹は味覚が変わったようで、子どものようにはしゃいでそれを食べた。
「あの喪服、捨てちゃえば?」
焼き魚定食を食べる二人を見ながら、私は素麺を啜る。つるつるとした細い麺で口の中がいっぱいになる。
「ちょっと」
「だってサイズ合ってないじゃん」
息子の横で香さんは申し訳なさそうに私を見た。いつの間にか、気遣ってもらうのがいつも通りになってしまったなと思う。息子も彼なりの方法で私を心配してくれているのだろうから、こちらこそお詫びの一言でも言うべきなのかもしれない。
「あの、もしご迷惑じゃなかったら……」
香さんの友人は仕立て屋を営んでいるという。高価なものではないし、サイズも合わないから新調しなきゃと思っていた。けれど、そのまま捨ててしまうには、この服には記憶が残り過ぎている。
「なら別のものに作り変えるなんて、どうですかね」
翌日は雲一つない晴天だった。香さんに連れられてお店の前まで辿り着く。横から見た香さんのお腹はもう膨らみがはっきり分かるようになっていて、ゆっくりとした動きで扉を開けた。お腹の中に新しい命を宿すこと。それはとても大変で、愛おしいことだと知っている。まだ名前のない男の子。全然違うけれど、私は妹を思い出す。
店員さんは喪服の状態を確認しながら一通りの説明を終えた。生地がしっかりしているから、色々なものにできそうだと言う。
「ほんとに何でもいいんですか?」
「できる限りがんばります」
朗らかな店員さんと、同じくにこやかな香さんは、私の答えを待っている。
熟考の末、私は「ズボンが良いかな。動きやすくて、子どもたちにも負けないくらい丈夫なやつ」と注文した。
一週間を待たずして、喪服は綺麗な黒のワイドパンツに生まれ変わった。
私は、それを履いてもう一度、保育士として働く自分を想像した。その隣にはまだ見ぬ初孫と、なぜか、妹の笑みがある。





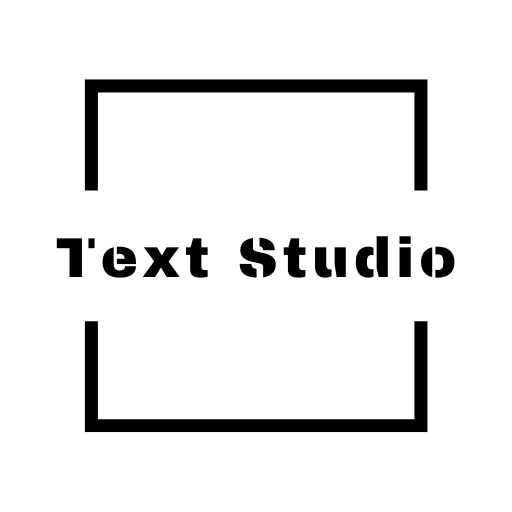


コメント