
金木犀の君
最初に見かけた時は、ただ器用な人だなと思った。
高校の入学式から数ヶ月後、俺は朝6時にかけた目覚ましの訴えに抗いながらも、学校へ行く身支度を整え、眠い目を擦って家から学校に向かう。その道のりは、まず自宅から駅まで車がまばらに行き交う車道の横を15分ほどかけて歩き、電車で2駅先にある目的地に到着する。本来は1時間も掛からない登校時間は高校生活に慣れて本当なら飽きるところだったが、俺の場合は少し違った事情がある。
「…また読みながら歩いてる」
家から駅までの徒歩の途中、自分の前を歩く一人の女子生徒を見つける。肩より少し長いセミロングの髪を揺らし、黒いピンで真ん中分けの前髪を留め、開けた視線を手元の本に向けながら、彼女の足は止まることなく歩みを進めていた。
すぐに読み終わる本であれば転ぶ心配もしなかったのだが、むしろ持っていた紙の束は毎週買っている雑誌の厚さの3倍ほどの分厚いもので、どう考えても15分では読み切れない。
そして、転んでしまうかもしれないと毎回ハラハラしているこちらの気持ちにも気付く様子はなく、まるで額に目があるのではないかと思わせる動きで綺麗に障害物をよけていった。
そして今日も、彼女は何事もなかったように駅まで無事歩き終えてると何事もなかったように改札を通っていく。
こうして俺は、不思議な女子生徒がどうしても気になって毎朝同じ時間に家を出ていた。
ーーー
時は進み、今は昼休み。俺はいつものように屋上で友人二人と飯を食べ始める。
まず最初に話をし始めたのは、いつも律儀に栄養バランスの整った弁当を持ってくる篝木瑛都(かがりぎ えいと)だ。
「春川静馬(はるかわ しずま)。今日は、彼女に声かけたのか」
「いや、全く」
まるで裁判を受けているかのように問い詰められるが、俺はその雰囲気に飲まれまいと普段通りの態度で答えた。
「そうか。なら、ストーカー確定だ」
「俺も異議なーし!」
あまりにも強引な裁判官の極端な判決に、もう一人の友人である縁真與(ゆかりま たく)も同意の声を上げる。そして持ってきていた購買の焼きそばパンを3口で食べ切ると、もう一つの惣菜パンの手に取り袋を開けていく。もうこいつらは面白ければなんでも良いのだと分かりつつも、俺は自分の尊厳を守るため反論の言葉を述べていった。
「偶然、駅に向かう道とその時間が同じなだけだし」
「だが、追いかけてなくとも合うように家を出てることもまた事実」
「俺だってその時間が丁度良くてだな・・・」
「静馬、少し遅く出ても間に合うって言ってなかった?」
「……っ」
知り合ってから数ヶ月だけの間柄のくせに、本当に容赦がない。遂には逃げ場がなくなってしまい、あとに残された手段は黙秘だけとなる。
しかし、楽しそうな話もとい、人が抱える恋の話となれば男も女も関係なく当人から本音を聞きたくなるのも頷ける。俺だって自分自身の話でなければ、こいつらのように質問攻めにするだろう。
「ほら、吐けば楽になるぞ」
右隣に座っていた瑛都が、少しずつ俺の方へと近づき迫ってくる。
「ほらほらー」
そして、一緒に面白がっていた與も左隣から徐々に近づいて煽ってきた。ここで昼が終わるチャイムが鳴って、話を中断せざるおえないというチャンスでも来ないかと期待するも、始まったばかりの休憩時間はまだ20分以上もある。
こうして数分の間は口を閉ざしていたけれど、最終的には観念をして小さい声で答えた。
「本を読んでる彼女が、歩いてる途中で突然視線を外すんだよ」
「虫でもいたの?」
「気になる男がいたとかだろう」
「お前らなぁ…」
言えと強要してきた割に、好き勝手に話し始める二人をよそに話を進めていく。
「辺りを見渡してると思ったら、近くにあった金木犀見つけて喜んでたんだよ」
「金木犀かー!あれは遠くにあっても匂いで分かるよな」
オレンジを纏う小さい花。見た目は他のどの花より劣るものの、その植物から香る匂いは近くを通る度に鼻孔をくすぐる。彼女は駅へと向かう途中にある金木犀が近くにあると、頑なに下を向いていた顔をあげては、匂いのする方を見て幸せそうな笑顔を浮かべていた。
「その笑った顔がだな、その……」
「惚れたんだな」
「はい」
話の流れに乗せられて、ついに隠していた本音を口にしてしまった、しかも敬語で。
「でも名前分かんないんだよな、静馬」
「それなら、分かるまで“これ”でどうだ?」
瑛都がズボンのポケットに入れていた携帯を取り出してメモ帳に文字を打ち込むと、書き終えた画面を二人に見せた。
『金木犀の君』と
こうして『春川静馬が”金木犀の君”に恋をしている』と周囲に知らされることとなり、話が広まってから何度目かの朝が訪れていた。俺はいつものように気になっていた彼女改め、好意を持ってしまった彼女の後ろを歩く。
瑛都が言っていた「ストーカー」という言葉が一瞬脳裏に過ったが、今日までのことを振り返ってしまったら人として終わる気がして考えるのをやめた。
普段通りに普通の通行人として振る舞いながら歩いていると、彼女のポケットから布が落ちる。けれど本人は落ちたことに気付かずに行ってしまったので、慌てて拾うと思わず勢いで声を掛けていた。
「あの、落としましたよ」
本にしおりを挟んで本を閉じると、こちらを向く。
「ありがとう、ございます」
「あ、あの!」
受け取り再び本を開こうとする手を止めたくて、声を上げた。
つい引き留めていたが、咄嗟の行動に頭がついて行けず次の言葉が出ない。一歩、また一歩と離れていく彼女の後ろ姿を見つめていると不意に知っている香りに包まれていることに気づく。そして俺は咄嗟に“その花”のことを口に出していた。
「金木犀、綺麗ですね」
「え?」
下ばかり向いていた彼女は、その言葉に驚きハッとこちらを振り向いて驚いた様子を見せる。それもそのはず、偶然ハンカチを拾ってくれた人が、唐突に花が綺麗だと言い出したら誰だってびっくりもする。
歩道の真ん中で、二人きり。シュンシュンと何台も走り抜けていく車を横目に、話を振られた彼女は親切にも言葉を返してくれた。
「好き、なんですか?」
「えっと…その、悪いものを払ってくれるし、何より小さいのに綺麗ですよね」
正直、自分でも何を言っているのかさえ分からない。少しでも相手の印象に残ってくれたらいいと願ってそう答える。
「……そう」
そして返事は、至極真っ当な素っ気ないもので、まさに“のれんに腕押し”と言って良いだろう。けれど、その小さな反応の中に小さな笑みが浮かんでいるのが分かった。さすがに最初に金木犀を見つけた時に見せた笑顔ほどではなかったものの、本を読むときの無表情とは違う彼女の顔が眩しく見えて仕方なかった。
「じゃあこれで…」
呆然としてしまい返事をせずにいると、話を終えたことでその場から去ろうとする。さすがにこれ以上時間を奪うわけにもいかず言ってしまう相手の姿を見送りながら、俺は最後の最後に質問をした。
「あ、あの!名前は?」
「吉住 金木犀(よしずみ きんもくせい)」
その後は、どうやって学校に向かったのか全く覚えていない。きっと身体に刻まれた記憶の通りに手足が動いて、いつものように登校を果たしたと思う。
そんな魂を抜かれたように放心している級友を見るやいなや、友人二人が不思議そうに俺の様子を伺いながら声を掛けてきた。
「静馬が動かない…おーい!」
「どうした、ついに振られたかー?」
登校中のことを、まるで走馬灯のように脳裏に浮かべながら、それに見合う説明文を口にする。
「き……、金木犀の妖精さんがいた」
「「は?」」
ーーー
一方、同時刻の別の学校では、一人の女子学生が教室に入って自分の席へと座った。
いつもなら忘れた教科書を貸して欲しいと第一声に言ってくるクラスメイトが、珍しく質問を問いかけてくる。
「きぃちゃん、どうしたの?」
「え?」
「いや、なんか顔が嬉しそうだったから」
私の名前を決めたきっかけは、母が入院していた病院に金木犀があったからだという。
そう語る母曰く、この花がなければ私の名前は別のものになっていたかもしれないと笑い話にしていたが、花の名前と同じ「金木犀」と名付けられた子供は、一度集団の中で名乗ってしまえば質問攻めにあい、秋になれば必ず話題にされてしまう。
『なんで、金木犀って名前なの?』
『金木犀ってあの花の?』
『金木犀の匂いってどこかでも分かるよね』
『ほら、金木犀あげようと思って取ってきたの』
それをたった数年でも繰り返していれば、いい加減嫌になって花を見たくもなくなるのだろう。けれど私にとって金木犀は見た目も香りも嫌いになれなくて、あの香りがあればどこに木があるのか探してしまうほどだった。
「嫌いだけど、好き」という、そんな矛盾を抱えていた矢先だった。
『金木犀、綺麗ですね』
いつだったか、昔どこかの英語教師がとある英文を愛の言葉に訳した際、好きや愛という言葉を使わずに別のものと言い換えてそれを表現したという。
ハンカチを拾ってくれた彼はそれを何気なく伝えてきたつもりだろうし、きっとそういった意味で言葉にした訳ではないと分かっていても、それでも。
「なにかいいことでもあったの?」
「あった、かもしれない…」
嬉しいと思ってしまった自分がいたことを否定はできなくて。
心のどこかでまた、声をかけてくれたらいいなと思ってしまっていた。
この出会いから、二人の関わりはもっと深くなっていく。
そして、あの彼が金木犀の前でもう一度同じ言葉を伝えるのはもっと先のお話。

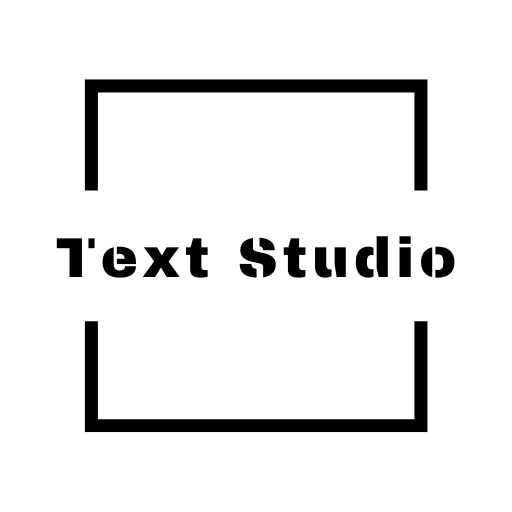




コメント