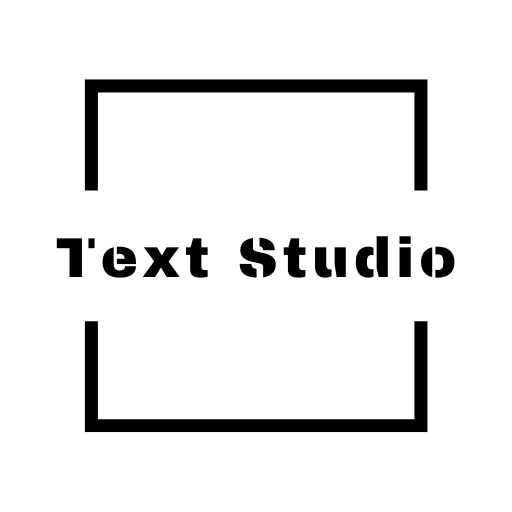
第二次ヴェルサイユの戦い
以前投稿した、エマとバースが出てくる章の続きになります。もしよろしければ、前編を読んでからお楽しみください。
本編(プロットポイント①からミッドポイントまで)
(着任後初の戦闘で死傷者多数。それを引きずって無理な訓練をするバース。)
目の前に立つ青年は、激しい息遣いと、小刻みに震える筋肉が伝える限界を押し殺して、無謀な何度目を始めようとしていた。エマはそんな彼を、黙って見つめていた。
「まだやれます」
「……いや、今日はここまで」
「嫌です、もう一回だけ!」
「こっちが限界なの。もう見てられない。その手、元に戻らなくなるよ」
その気遣いに目で返すバースを見て、エマはふいと天井の隅を見やる。
「ハァ、そんな顔しないでよ。気持ちは分かるよ、多分」
それだけ言うとエマは、未だ構えを崩さないバースを横目に、ジャケットを羽織り直して片付けを始めた。
「とにかく、今日は終わり。手は冷やしてもらいな」
訓練用のバトルスティックが収納されるのを見届けてから、出口の手前で振り返って
「言いたいことがあるならすぐ言いなよ。昔にかこつけてタイミングなんか見計らってちゃ、言えることも言えなくなるから」
そう言って、スライドするドアの向こうに姿を消した。
トレーニングルームに面した廊下に人影はなく、夜間を演出する保安灯と、嫌にぴかぴか光る自販機が目に悪い。
「私も、人のこと言えないなぁ」
突き当たりを曲がって、自室に繋がる廊下を渡りながら、彼女はかつての友人のことを思い出していた。
次の日の朝、朝礼を終え、未だジンジンと痛む右手を摩りながらバースが食堂に向かっていると、目の前の分かれ道の、食堂と反対側のギャザリングスペースから、遠くまでよく響く言い争いが聞こえてきた。片方の声の主はよく聞こえないが、どうやら食ってかかっている方はフィドルだった。
「朝っぱらから、元気だよ全く」
面倒事は御免だが、しかし放っておく勇気もないので、声のする方へ近づいていく。次の角を曲がったところだという近さまで来た。こっそり覗いてみると、フィドルと、同じ分隊の隊員二人が、言い争うもう片方へ寄ってたかっている。その相手は、エマだった。
「ふざけんじゃねぇよ!アンタに俺らの何がわかんだよ!」
「だから、出撃は許可できない。私が止めなくても誰かが止めるし、今出たら、みんな死ぬよ」
「黙れ!こっちはミドラを殺されたんだ!仲間一人やられて、黙ってろってのか!?」
「そのうち、また出撃要請が出る。今はその時までに傷を直すべき。今の君の状態じゃ、マトモにタイタンを動かせもしないでしょ」
「なんだと!」
エマの言う事は合理的で、実に的を射た指摘だった。しかしだからこそ、合理的な意見は、時に相手の逆鱗に触れる。
「アンタ、上官だからっていい加減にしとけよ!アンタに分かんのか?ダチ一人守れねぇでノコノコ生きちまった俺達の気持ちがよぉ!」
上官への反抗は重大な規律違反だ。しかし、そんなことはお構い無しにフィドルはまくし立てる。
「ちょっとは言い返してみたらどうだ?見下すみてぇでキモイんだよ。冷酷無情ってのは、アンタにお似合いの言葉だな。どうせ誰かを失った経験なんか無いんだ。無いからそんなに冷静でいられるんだろ!?」
フィドルがそう罵った時、エマの目が一瞬大きく見開いたような気がしたが、取り巻きに隠れて、良くは見えなかった。
「チッ、顔色一つ変えねぇ。行くぞ。こんなヤツに仲間の大切さを説いてやるなんざ、酸素がもったいねぇ」
フィドル達が去った後も、エマはしばらく動かなかった。ただ俯いて、拳を握り締めるだけだ。バースはどうしていいか分からなくて、少しの逡巡の後、結局、後ろめたいまま食堂へ向かった。
その日の昼過ぎ、訓練が終わってタイタンの調整をしている途中で、バースはエマに声を掛けられた。
「ねぇ、バース君」
「え、なんですか?」
「ご飯行こうよ」
「……え?」
バークト星系 FCCサラトガ 七番民間ターミナル カフェ「ヴァルピス」
「ヴァルピス」のレモンスカッシュは、近隣の州から、それ目当ての客が来る程に評判が良い。サラトガからも拝むことができる農耕惑星サン・ナルデリーノで採れた新鮮なレモンは、香りが良く、またレモン自体が甘いので、これを使ったレモンスカッシュは、野趣に富んだ甘酸っぱさが鼻腔をくすぐる、魅惑の一品に仕上がるのだ。
しかし彼は、ここのレモンスカッシュが嫌いだった。
バースはレモンスカッシュを求めて並ぶリピーター達を見て、どうしてこんなにもこの店が人気なのか、下世話な勘繰りで暇を潰していた。
店の向かいの柵にもたれかかって、何分待つのか知れない長蛇の列を眺めながら、自分も、自分の上官を待つ。プライベートで会うのは、これが二度目だ。
「『野趣に富んだ甘酸っぱさ』って。味が薄いって正直に言えばいいのにさ」
そう店先に放り投げた独り言の首根っこを掴んで、無理矢理会話に変えてくる声があった。
「ひどいなぁ。私、ここのレモンスカッシュ好きなのに」
言葉の割に気に留める様子のない彼女が突然表れて、バースは咄嗟に右手をカーゴパンツのポケットに突っ込んだ。
「あ、お疲れ様です。エマ少尉」
「うん、じゃあ、行こっか」
そうして二人は、ターミナルから、食欲そそる暴食街の香りの中へと消えていった。
(改めて、デカイ人だなぁ)
大股なエマの横を速足で着いて行って、バースは足が長いエマが羨ましくなった。
向こうから誘っておいて合わせる気のない歩調に気まずさを感じながら、エマに付いて行く。そんな気まずさを感じ取ったのか、一瞬バースの方に目をやって、彼の頭から爪先を舐めるように見たあと、エマの方から話しかけた。
「服、そんな感じの着るんだね」
「え、あぁ確かに。私服で少尉と会うの、初めてですね」
エマは、初めて会ったときと同じ茶色のハーフジップのセーターと、その上から羽織った黒いロングのダッフルコート、それにベージュのスラックスを履いた、シックで落ち着いたコーデ。対してバースは、クリーム色のデニムジャケットに赤のニット、黒のカーゴパンツを合わせた、いかにも若者らしい、流行りのウェスタンコーデだった。
「いいじゃん」
「どうも」
予想外の評価に、よそよそしく返して、自分の服を眺めてみる。お気に入りの服を褒めてもらえるというのは、気分が良くなるものだ。
ふとエマの方を見てみると、一瞬だったが、彼女の横顔が、笑っていたように見えた。エマが笑ったのをバースが見たのは、あの日以来、初めてだった。
「少尉は、前とおんなじですね」
「前?」
「ほら、着任前のあの日」
「あぁ」
バースに言われて思い出したような顔をしたが、つい二週間前のことだった。本当に忘れているなら、心配になるなとバースは思った。
「あの店、美味かったなぁ」
「今は行ってないの?」
「はい、着任してからは、一回も」
「そっか」
行くとあの日のナンパを思い出すからだとは、口が裂けても言えなかった。
「じゃあ今日で二回目だね」
「え?」
そう言われてふと正面を見ると、外からも目立つ見覚えのある円窓が目に飛び込んできて、バースは脳髄を掻き回されるようなむず痒さに襲われた。
恐る恐るエマの方を見ると、にへらと楽しそうな笑みを浮かべていた。年の離れた弟をからかうような、そういう屈託の無さだった。
「さ、入ろっか。オニーサン」
__しまった
店に入ると、小柄な店主が厨房からひょっこり顔を出して挨拶をしてきた。
「イラッシャイ!アーあの時ノ!よく来たネ!ササ、好きなトコ座ってヨ」
十八時過ぎの店内にはポツポツと人が入り出していて、恐らく第七星系艦隊の所属らしい軍人が、大盛りの炒飯や麻婆豆腐をかき込んでいる。
エマとバースは、円窓の際に並んだ二人掛けの席に座った。
「からかってるんですか」
その問いに答えるように、エマはカウンターに掛けられたメニューの札を眺めつつ、肩をすくめる。
折角、気になっている女性と食事だというのにこれでは、心臓に悪い。
「ハァ、まぁいいですけど。ああそうだ。少尉ってコレ、いいですか?」
そう言って、バースはジャケットの内ポケットから電子タバコを取り出した。
懐から現れたタバコに、エマは目を丸くして驚いた。
「吸うの?」
「まぁ、意外ですか」
「うん。いいよ、吸っても」
了承を得て、切れかけのリキッドを替えながら、エマに聞き返す。
「少尉は吸わないんですか?」
「体に悪いもん。それに、何がいいのかさっぱりだね」
ふぅんと返事をして、タバコに火をつける。最初のひと吸いを頬杖しながら眺めていたエマは、はっと気が付いたことがあって、口を開いた。
「……それのせいじゃない?」
「え」
「レモンスカッシュ」
料理が運ばれてくるに連れて、二人の会話は弾んだ。空のグラスが回したアルコールがゆっくりと、上官と部下という隔たりを融かしていく。
「少尉って、背高いですよね。いくつあるんですか?」
「百七十九、だったかな」
「ひゃあ」
バースの悲鳴に、エマが不服そうに聞き返す。
「何、聞いたのそっちでしょ。君こそいくつなの」
「四月に計った時は、百七十五でした」
丁度良いアドバンテージを取ったエマが、にへらと笑う。
「ちっちゃ」
「真ん中くらいですよ。陸軍のやつらとかゼロジーエクササイズやってるのとか、あれが変なんですよ」
むっとして言い返すバースの反論を、エマはウーロンハイのグラスに注いで、一緒に呑んでしまう。
言い返しがいのない人だな。
そう思いながら、メニューの札を端から眺めていると、エビチリと書かれた札がバースの視線を止めた。
「エビチリか。すいません!エビチリ一つ!」
「ハイヨ!」
厨房から元気に手を振る小柄な店主を見ていると、バースは彼がこの前話してくれた身の上を思い出した。
「そういえばここの店主、もともとアウターローの自警団にいたらしいですね」
「へぇ、そうなんだ」
エマが横目で店主を眺めながら、ウーロンハイを舐める。
「自警団っていうと、やっぱ何かしらパイロットだったんですかね」
「どうだろう。けどあの人だったら、ぶつけることは無さそうかな」
バースはエマの言った意味がよくわからなくて、きょとんと首をかしげる。
「どういうことですか?」
「あれ、バース君っていつ入隊したの」
「ルナリベンジの、ちょっと前です」
「あぁ、じゃあ知らないか」
エマが四杯目のウーロンハイをくいっと飲み干して、語りだした。
「ちょっと前、えっと、いつだったかな。とにかく前の世代のICC(直観的戦闘制御)はね。ダイレクト投影システムって言って、操縦桿を振り回して、その動きをトレースさせてタイタンを動かしてたの。ほら、こんな風に」
箸を両手に持って、コクピットを真似するエマを見ながら、バースの脳内に、とても初歩的な疑問が浮かんだ。
「え、危なくないですか」
バースの指摘を受けて、幼稚に両手を動かしていたエマはピタッと止まって真顔になる。
「うん、危ないよ。普通に怪我してる人とかいっぱい居たし」
「なんでそんな危なっかしいモン使ってたんですか……」
「だって強いんだよ?それこそテルミドソードとかさ、好きなように振り回せるし」
エマは楽しそうに思い出に浸っているが、バースが若干引いていることには気づいていなかった。
「それで、少尉は、怪我とかしなかったんですか」
「指の骨にひびが入ったくらいかな」
エマが得意げに腕を組む。
「なんせ私、強いからね」
ツッコミを入れようとしたバースだったが、自分が訓練で彼女に一度も勝ったことがないのを思い出して、鹹豆漿ではぐらかす。軍人というのは変な人種だなと新しい料理を頼もうとしたとき、すっかり忘れていたエビチリがテーブルに運ばれてきた。
「ハイ、エビチリお待たせネ!」
「あぁ、ありがとうございます」
「ねぇ」
エマが、突然口を開く。
「自警団に居たんでしょ。パイロットだったの?」
急に店主に問い掛けるエマにびっくりして、バースは鹹豆漿を吹き出しそうになった。
「少尉⁉急に何を」
「気になるじゃん」
「だからって」
店主もバースと同様、突然のことに目をパチパチと瞬かせていたが、すぐにニコリとした表情に戻ってエマの質問に答えてくれる。
「私カイ?私はそんなハナヤカなポジションじゃなかったネ。秘密ヨ秘密。ジャ、ごゆっくりネ~」
そうニコニコと身を翻して、また厨房に戻っていった。
ホッと息をつくバースだったが、彼とは逆に、エマはその回答に納得いかなかった様子で、二の腕に頬を預けながら、ぽやっとした顔をしかめてクレームを入れ出した。
「秘密って言われたら、余計気になるじゃん。ね」
共感を求めて、バースに目配せをする。
「ちょっと少尉、気を付けてくださいよ。プライベートな話題なんですから」
「でも、気になってたでしょ?」
「そりゃあ、気にはなってましたけど」
バースはちょっと申し訳なさそうにしつつ、箸でつかんだエビチリを口まで運んだ。
「ん、このエビチリ、結構イケますね」
艶やかな甘辛いソースが、プリッとしたエビによく絡んで、美味しい。
「一個ちょうだい」
エマが体を起こして言う。バースが、あからさまに嫌そうな顔をする。
「じゃあ、青椒肉絲あげるから」
そう言ってエマは、さっきまで肴にしていた、やけに緑の多い青椒肉絲の皿をバースの方に動かした。
「野菜しか残ってないじゃないですか!」
「苦手なんだよ、特にこういう、青いやつは」
「子供じゃないんだから」
「死活問題だよ」
「んな大袈裟な。ま、じゃあ貰います」
「やった」
エマを見ていると、バースはよくその人が分からなくなる。冷静で口数も少なく、凛とした立ち振る舞いからは、軽妙洒脱な大人の女性といった印象を受けるのだが、食事の好みや仕草などからは、幼い少女の影が見え隠れする。彼なりに説明してみると、シュガースティック二本のブラックのようなそういう、背伸びした大人っぽさだった。
「もしかして少尉、酔ってます?」
「多分、酔ってないよ」
「酔ってますね」
「酔ってないっ」
そう言い返しながら、両手でテーブルをポンと叩いてぐいとバースに近づく。
「まったく、上官に向かって失礼じゃない?」
そうボヤく、箸を持ち直す手がおぼつかなくて、やはり酔ってるなと、ハイボールを口へ運びながら見つめる。
「ベロベロじゃないですか……。ていうか、まだ食べるんですか?」
「まだ食べるよ、これだけしか食べてないのに」
これだけとは言ったものの、既に大皿二つと中皿を一つ平らげ、炒麺にも手を付け出している。
「いやぁ、結構食ってますよ?もうその辺にしといた方が」
そう言って、炒麺の行く末を不安げに見守る。その視線に気づいたエマが、自分の方に皿をぐっと引き寄せた。
「あげないからね」
バースを軽く睨んで来て、こっちを見つめるオレンジの瞳と目が合う。改めて面の良さに気付いて、ポッと赤くなったバースは顔を逸らした。
ハイボールを飲み干して、チラッとエマの方を見ると、美味しそうに炒麺を頬張っている。こういうのは、子供だ。
「いりませんよ。ていうか、太りますよ」
「いいんだよ、動くからね」
結局、二人が店を出たのは、エマが中皿をもう二つと、ウーロンハイのグラスを七回空にした後のことだった。
「美味しかったねぇ」
そう、上機嫌で歩いているエマの少し後ろを、バースはタバコを吸いながら着いて行った。昔、強い兵士はよく食う兵士だと祖父が言っていたが、どうやら本当らしい。
「俺、今タイタン乗ったら絶対に吐く自信あります」
バースの弱音に、エマがフンと鼻を鳴らして自慢げに返す。
「まだまだだねバース君。そんなんじゃあ、次またアレと戦うってなっても__」
と、そこまで続けて、突然エマがしゃがみ込んだ。何事かとバースが駆け寄って顔を覗き込むと、真っ青。
「気持ち悪い」
サラトガの中は既に夜間帯に入っており、街灯と、壁に取り付けられた保安灯だけが道を照らしている。
バースはコンビニで水のボトルを買って、隣接された公園で待つエマに差し出した。
「はい、お水」
「ありがとう」
そう礼をして、受け取った水を少しだけ口に含む。
「酔い、ちょっと覚めました?」
「うん」
「普段から、あんなに飲んでるんですか?」
バースは素朴な疑問を投げ掛けた。確か、初めて会ったあの日は、酔ってこそいたが、今日ほどではなかった。
「いや」
ふぅーっと大きく息を吹く。
「今日はちょっと、飲み過ぎちゃったね」
声色から、先ほどよりかは『出来上がっていない』エマだと気付く。
当の本人は立ち上がって、窓際まで歩いて柵にもたれかかった。バースはそれを黙って見ていた。思い当たる節は、確かにあった。
「今朝の、アイツらですか」
返事は無かったが、恐らく当たりだろう。
「少尉って、ここに来る前、どの部隊にいたんですか」
少し間を置いて違う質問をしてみるが、また返事は無い。だが、柵に腕を置いた彼女の肩が揺れて、ついたため息は小刻みに震えていた。
意外と弱い人なんだ。バースは、心の中でそっと呟いた。多分、あんなに飲んで食っていたのも、やけ酒だろう。ちょっと思うところはあったが、それは言わなかった。
しばらく経って、タバコを一本吸いきった頃、腫れぼったい目のエマが柵を離れて、こっちを向き直った。
「着いてきて」
バースは何も言わずに後ろを追う。
先程の酔いが嘘のように静かに歩くエマの背中は、漠然とした寂寥が付き纏い、どこか重たげだった。
「やっぱり、飲みすぎたなぁ」
「……無理は、しない方がいいですよ」
「フフッ、君が言えたことじゃないけどね」
「あれは__」
喉から咄嗟に出た否定は、それ以上には繋がらなくて、宙ぶらりんのままで窓の外に飲み込まれた。否定しようとすればするほど、昨日の右手がしんしんと痛む。右手はまだ医者に診せていなかった。医者に診せたら、自分の限界を知らされるような気がして、それが怖かった。
「月並みだけど、出来なかったことを引きずっても、良いことないよ。人って、後ろを向いたまま前に進めるほど器用じゃないからね」
「背中に目を生やす努力を阻むような言い方は、嫌いです」
「それが自己保身だって言ってるの。そんなのはどこまで行っても言い訳だよ。霞を掴むようなことしてても仕方ないでしょ」
エマの説教は、千切れそうなほど耳の痛い話だった。否定された辛さよりも、懊悩の末の最善策として、霞を掴もうとしていた自分の若さと、仲間への不誠実が、バースにとってあまりにグロテスクだった。
「常に、次どうしたいかを考えて準備をするべき。って、私も最近気付いたんだけどね」
「でもそれは」
「そうだね、でも薄情かどうかは多分、自分で決められるよ」
「そんなに強くないのも、自分ですよ。結局は他人ありきですから」
「……さ、ここだよ」
着いた先は、民間用のシャトル乗り場だった。
「クーペンコローゲまで、軍人二枚」
「え、今からですか!?」
「一時間もあれば行って帰って来れるよ」
「いや、そうですけど」
多少の抵抗はあったものの、二人は、片方は渋々乗り込んで、シャトルは出港した。機内サービスで、エマはジンジャーエールを頼んだ。バースはタバコを吸っていいかCAに尋ねたが、今年から禁煙になったのを忘れていた。
「ご搭乗の皆様にお知らせいたします。本機は間もなく、クーペンコローゲ、タレン・ホルト連邦宇宙港に到着いたします。大気圏突入の際、機体が多く揺れますので、シートベルトを着用して、座席に深くお座りいただきますよう、お願いいたします」
合衆国首都クーペンコローゲD.T. ウィーブスバッグ英霊墓地
6月のクーペンコローゲは肌寒く、ニットとデニムジャケットでは心許ない気候だった。
「寒くないですか?」
「すぐ着くから、我慢して」
そうして向かった先は、軍営の花屋だった。
「すみません、バーデンベルギアを」
軍では、よく人が死ぬ。だから国防省は農務庁と連携して、軍人や遺族が献花する為の花を生産・販売・提供するソルジャーフローリスト公社を運営している。
「墓参り、か……」
店員と親しげに話すエマを窓の外から眺めながら、今朝のフィドルの言葉を思い出す。もし墓参りなら、フィドルは死んだら地獄行きだ。
しばらくしてエマが、バーデンベルギアと呼んでいた花を二、三本抱えて店から出てきた。
「行こっか」
街の光に沈むウィーブスバッグには街灯の類は無く、二人は墓地の中を走る、土で押し固めただけの簡素で暗い小道を歩いていた。十分くらい歩いただろうか。エマは汚れの少ない、比較的新しい墓石の前でふいに止まった。エマが止まったので、バースもつられて立ち止まる。
「ドルビンスク・アシモフ、中尉。てことは、上官ですか」
「ううん、士官学校の同期」
「ああ」
墓石に花を手向けて、少しの間しゃがみ込んでいたエマが立ち上がると、バースはベンチに促したが、エマの方が、最終便が近いからと言って、来た道を戻りながら話すことにした。
「ていうか、朝のやつ、聞いてたの?」
「え、あぁ、はい」
「聞いてたんなら、止めてくれても良くない?」
痛い所を突かれてしまった。
「いやぁ、なんと言うか。あそこに割って入れるほど、度胸もないですから」
「薄情者」
「……すみません」
実際、フィドルの発言が本当であろうがなかろうが、止めるべきだったとバースは反省していた。
結局あの後フィグス達は、上官に対する反抗と無断出撃で、五日間の営倉入りを命じられた。なのでエマとしてはもうどうでもよかったのだが、本人が落ち込んでいるようなので、意気地なしな部下の薄情を許してやる。
「ハァ、いいよ。アイツらは営倉入りだし、もうあんまり気にしてないから」
そう慰めるものの、彼なりにはまだ思うところがあるようなので、彼のことは放っておいて、エマは話を続けた。
「私はね、前、167星系艦隊にいたの」
それを聞いて、俯いていたバースがエマの方を向く。
「167?じゃあ、ゲルガーに行ってたんですか?」
「行ったよ」
「もしかして、アシモフ中尉も、そこで」
「うん」
バースは、ちょっとつっかえたうんのあと、エマの歩く速度が少し遅くなったのに気付いた。だんだん遅くなってそして、完全に止まった。少しして、バースが決まりの悪そうに話しかける。
「えっと、少尉?」
「昨日さ、言いたいことは言えるうちに言いなよって、言ったよね」
「はい」
「私はアシモフに、言えなかったの。言いたかったこと、言わなきゃならなかったこと。だから、君には、そんな思いをしないで欲しい」
「……はい」
また二人は歩き出した。最終便までは時間がある。
「フィドルのことですけど。なんで、言い返さなかったんですか」
「なんでって、いちいち言い返す程のことでも無かったし。不幸自慢をするのが軍人なら、それってちょっと悲しいよ」
「でも、だからってやけ酒は勘弁して下さい」
「ごめんって」
ちょっと申し訳なさそうにそっぽを向く。一応、迷惑をかけた自覚はあるらしい。
「まぁ、そうだなぁ。私は、仲間が死なないで済むなら、それが一番だから」
「お人好しですね」
「アシモフに頼まれちゃったからね。兵士が駒として死ぬ事の無い軍隊を作って欲しいって」
また、エマの歩みが止まった。空を見上げて、見上げた空では、議員都市を迂回してきたストームブリンガーとウーラノスの飛行隊が、二人を飛び越して行った。それなりに低い所を飛んでいたので、エンジンの轟音が一瞬、英霊墓地の静寂を掻き乱した。
「駒として死なない、ですか」
「うん、アシモフが昔、ナントカ少佐って人に頼まれたんだって。それをまた、私も頼まれたの」
「どういう意味なんですか、具体的に」
「さぁ、わかんない。聞く前に死んじゃったから」
他人がずけずけと入る領域でないことは承知していたが、死んだ戦友の遺言にしては、随分淡白だなとバースは思った。
「そんな感じでいいんですか」
「いいと思うよ。受け継いだからって全部背負ったら、それは自分じゃないと思うし。受け継いだ人によって、感じ方や捉え方だって変わる。全く同じなんて無理だよ」
風が吹いて、靡いた髪が彩ったエマの微笑を含んだ横顔を、バースはじっと見つめている。
「だからまあ、言い出した人が、どんな気持ちで最初にそれを言ったのか。それをちょっと考えるくらいで、充分だって思うけどなぁ」
そう言ってコートの襟を立てるエマを見ながら、
「そんなもんですかね」
「そんなものだよ」
それきり、二人の会話は終わった。
墓地からまた十分程歩いて、宇宙港の城下町に入る辺り。先に口を開いたのは、エマの方だった。
「今日、ありがとうね。だいぶ楽になった」
「えっ、いやぁ。感謝されるようなことは、なんにも」
「謙虚だねぇ」
返す言葉が見つからなくて、そもそも返す必要も無いと気付いて、バースは、今では珍しいレンガ造りのビルにもたれ掛かる。
城下町は、宇宙港の騒音が理由で住民はほとんどおらず、夜はひっそりと静まりかえる。往来の無い深夜のダウンタウン、マスドライバーとランチパッドが照らすその影で、立てた襟を抓んで引き寄せる。
「……少尉、やっぱり酔ってますよね」
「酔ってないよ」
共通時二十一時五十八分発のマスドライバーが、轟音を立ててシャトルを打ち上げる。
「甘」
「なんか、ザラザラしてる」
「タバコのせいじゃないですかね」
「……君も、酔ってるでしょ」
「…………多分」
戦争中だと言うのに、繁華街はこんなにも明るくて、それが嫌になる軍人も多い。
だが今夜は、仄暗い殺し合いをひた隠す。
サラトガ行きは、次で最終便だ。
翌日の実習訓練で、何故か終始顔の赤いバースといつにも増して仏頂面のエマに、同じ小隊の隊員が真相を聞き出そうとしたが、勝ったら教えると言われた挙句、隊員は医務室に担ぎ込まれ、スイフト六機が再調達される羽目になった。







コメント