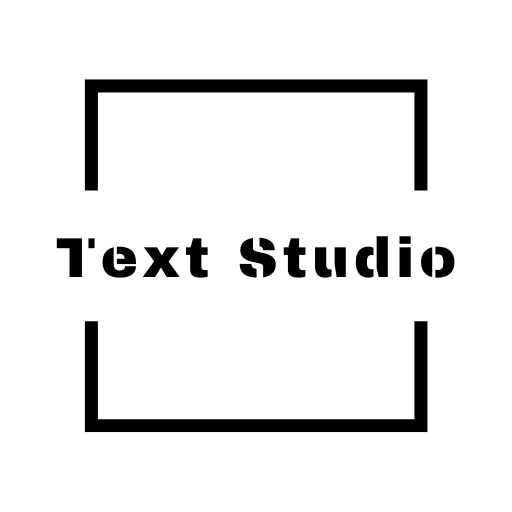
N.G.C.0245 4月20日 ウィルバード州 Wi46号宙域 サキモリ前哨基地Ⅽブロック
「聞いたか?バースクの件」
「聞いたよ、酷かったんだってな。」
「跡形もねぇとよ。議会は、バースクを放棄することで合意したらしい。」
「ま、国境地帯の性かね。」
「だな、たく惜しいことしたぜ。いつか旅行しに行こうと思ってたのによ。まさかこんなに早く…うおっ!」
そこまで言いかけたとき、コクピットが轟音で包まれ、ボリスは慌ててSSE(スペース・サウンド・エフェクト)のボリュームを下げる。何事かとHUDが示す方を見ると、USDF(合衆国国防軍)の”ガーランド”制宙スターファイターが三機編隊で飛び立って行くところだった。
「どうした?」
「いや、ちょっと耳を立て過ぎただけだ…。国防軍の連中、えらくピリピリしてるな。今日だけで何度目だよ。」
「大方、バースクが落ちたってんで、上の連中が慌ててんだろ。軌道爆撃なんか久しぶりだったしな、気持ちはわかる。」
「そういうの、杞憂っていうんだぜ」
「ハハ…、おっと、もう交代か。」
ヒッグスのスパルタン級タイタン”アイビス”がポートの方を向く。ずいぶん人臭い動きだ。ICCを使いこなしている。
タイタン、正式名称「二足歩行型戦闘航宙機」。この25メートルの巨人のおかげで、ボリス達パイロットは苦労して終えた訓練過程を一から受けなおす羽目になった。戦闘航宙機と銘打っておきながら手足の生えたその機体は、アビオニクス、FCS、OS、運用方法、どれをとってもスターファイターと共通する箇所が見当たらない。それだけならまだ無用の長物としてかわいがってやったのだが、この兵器の憎いところは、これがスターファイターよりも遥かに強かったということだ。
スターファイターよりも打たれ強く、スターファイターと同等、あるいはそれ以上の機動力を持ち、武装の幅も遥かに広い。タイタンは、現れてからのたった3ヶ月で、スターファイターから主力の座を奪い取ったのだ。
公国軍のタイタンと戦ったスターファイターが初めて生還したとき、ボリスは格納庫で始終を見ていた。コクピットから血相を変えて飛び出してきたパイロットの、グロテスクな表情を忘れることができない。
そのパイロットは2日後自殺した。あんなものと戦うくらいなら、と、将校用のカトラリーからフォークを盗んで首を四回刺したらしい。次の日、将校用のカトラリーは樹脂製になっていた。
そこまで思い出して、ボリスはハッと我に返った。気を抜くとこれだから、最近は寝つきが悪い。
「ようボリス、今日は時間ぴったりに来たぜ?」
ハーディーが軽口をたたきながらRCSを吹かしている。
「みたいだな、今夜は絵本でも読んでやろうか?」
「パパ、アタシもうティーンよ?絵本くらい自分で読むワ!」
分隊一番の若手、キールがわざとらしい裏声で割って入る。
この23歳の新入りは、タイタンが主力になってから入ってきたいわゆる「タイタン世代」の人間だ。タイタンの動かし方については、熟練パイロットよりも手慣れている。
「おいキール、今度は誰の真似だ?」
とボリス。
「うちの妹ッスよ。この前久々に家に帰ったらこれなんで、頭痛ぇったらないです。」
「まぁ、とりあえず後は頼むからな、二人とも。」
それだけ言って、ヒッグスはそそくさと格納庫へ帰っていく。ボリスも後を追う。
機体を屈めて、背中の”ライカン”バトルブースターをぶつけないよう慎重にRCSを吹かす。
ポートを少し進んで、格納庫まであと半分というところまで来たとき、ヒッグスがボリスを世間話に誘った。
「なぁ、こいつのブースター、ここのポートには不向きなんじゃないか?」
「もともとスターファイター用のポートだからな。タイタンには窮屈だろうさ。」
タイタンをメカニックに預けた二人は、その足で重力ブロックのラウンジへ向かった。
「交代まであと3時間ってところか、どうする、何か食うか?」
ボリスが返す。
「いや、食った後に連中が来たら面倒だ。今回はいい。」
「杞憂なんじゃなかったのか?」
痛いところを突かれて、ボリスは無精ひげに覆われた頬をポリポリと掻いた。
ラウンジに着くと、中は普段よりも騒がしく、いつも座っていたテーブル席には先客がいた。
「今日は多いな。」
ボリスが悪態をつく。
「国防軍の奴らだ、今朝警備隊の増強ってんでカルダモア(フリゲート艦)が来てたろ?それだよ。一体なんだってんだ?そこまで信用ならないかね、俺たちRRFは。」
「そう言うなよ、向こうにもメンツってもんがあるのさ。」
「ラウンジを我が物顔で使うのも、メンツの内かよ」
「カウンターしかないな。」
「どこでも構わねぇさ」
そう言って、ラウンジの端にあるカウンターに並んで座る。
サキモリの一般兵用ラウンジは無愛想なインテリアで有名だった。そんなラウンジの端にあるカウンターには、下馬評に甘んじた冷たいパイプのカウンターチェアが、これまた無愛想に並んでいた。
「いつんなったら改善されるのかねぇ。」
硬いパイプが尻に食い込む感触に、ボリスは一瞬顔をしかめる。
「なににする?」
そう言いながらヒッグスは、備え付けのホロプリントをぼうっと眺めている。
「いつものでいい、ウェスタンブレンドのアイスだ。」
「では、私も同じものを。」
ボリスのぶっきらぼうな注文の後ろから、落ち着いた男性の声がウェスタンブレンドのアイスを注文した。咄嗟に二人が後ろを向くと、RRFの制服を着た士官が後ろ手を組んで立っている。
少し面長のその士官は、ヨーロッパ系の伊達顔で、溌剌とした目と少し緩んだ口元が、優しい笑みをこちらに向けている。
左胸の階級章は、彼が少佐だということを静かに伝えていた。
「隣、いいだろうか?」
立ち上がろうとする二人を手で制しながら、カウンターに目くばせをする。
「もちろんです!ささどうぞ。ウェスタンのアイスでよろしいですか?」
「あぁ、ありがとう。」
ヒッグスと”少佐”のやり取りを聞きながら、ボリスは必死に記憶の棚を開け閉めしていた。見たことのある顔なのだが、どうも名前が思い出せない。どこかで会ったはずなのだが、どこだったか…。そうして口の中でうんうん唸っていると、ヒッグスが意図せず助け舟を出した。
「しかし驚きました。ユノー少佐がここにいらっしゃるとは。」
思い出した、シーブス・ユノー少佐。ボリス達の所属する第四戦隊の指揮官で、温和な性格で部下から慕われており、人格者でもあるとも評判の士官だった。ボリスは天井に向かってため息をついた。いくら最近多忙だったとはいえ、直属の指揮官を忘れるとは。
「いやなに、士官用のラウンジが国防軍の方々に占領されてしまってね、避難をばと思ってきたんだが、ここも大して変わらんようだね。」
「そうでしたか。ご同席できて、光栄です。」
「ハハッ、ありがたいが、そんなに畏まらなくともいいよ。…君たちは確か、ウチの部隊の者だったね。確か、第二小隊かな?」
「はっ、第二小隊のヒッグス・マッケンジー伍長と」
一拍置いて、ボリスも慌てて続く。
「はっ、同じく第二小隊、ボリス・ウィンドガード一等軍曹であります!」
「そうか、改めて、シーブス・ユノーだ。よろしくな。」
握手を交わしながら、なんと立派な方なのか。と、ボリスは思った。上官の名前すら忘れていた自分に比べて、少佐は百人あまりいる部下のひとりひとりまで覚えているときた。
「覚えていて下さるとは」
「部下のことを忘れるわけがないだろう。そこまで薄情なつもりはないさ。」
薄情者には耳が痛いお言葉だった。
「しかし、本当に多いね、国防軍。やはり、バースクの件かな。」
「戦々恐々といったところでしょう。狙いはやはり、第6JCT(ジャンクション)でしょうか。あそこには、唯一枝付けなしでD.Gに届く航路が走ってますからね。」
枝付けとは、ローゼンドライブ(ワープ航法)の際に行われる、任意区間でのワームホールからの強制離脱のことだ。枝付けは精密なジャンプが可能というメリットと、ジャンプジャマー散布下では使用できないというデメリットを同時に抱えている。
件の第6JCTと呼ばれるステーションには、合衆国首都であるクーペンコローゲD.Gに枝付けなしでジャンプできる航路が走っているため、戦略的重要地点としてその座標は秘匿され、このサキモリ前哨基地を介さないと到達できないようになっている。
「公国が狙うならそれだろうな。いくらジャマーを撒いても、出口まで道なりであるなら管制装置など不要だ。」
「厄介ですね、殺し合いは。」
「あぁ、本当に」
そう呟いたユノー少佐の遠い目を見ながら、それまで聞き手に回っていたボリスがようやく口を開いた。
「お嫌いですか?殺しは。」
その言葉に目を見開いて、ユノーがボリスの方を見る。
「分かるか?」
「いや、なんというか…顔に書いてあるといいますか…」
「そうか…そこまで顔に出ていたか…。あぁ、ありがとう。」
運ばれてきたウェスタンブレンドのアイス二つと自分のホットカフェラテを、ヒッグスがテーブルに並べていく。
「まぁ、好きでないとおかしい。とまで言いやしませんが、嫌々殺るのはお辛いでしょうに。」
「それはそうだな。ただなんというか…やはり嫌いとはまた少し違うかもしれんな」
ヒッグスがカフェラテに口を付けながら割って入る。
「というと?」
「私は、わざわざ殺さなくてもいいと思っているんだ、正確には。例えば、相手に戦闘の意思がなく、こちらも無理に殺す必要が無いなら、そこに殺しの道理は通らないだろう?」
「はぁ」
「それに、彼らだって人間だ。帰る家や、家族だってあるだろう。だから私は、もし彼らに叩くべき門戸と、懐かしむべき匂いがあるのなら、そこへ帰してやりたい。そう思っているんだ。」
なんというお人よしだ。とヒッグスは心の中で苦笑した。彼がなぜ人格者と呼ばれるのか、彼は少しだけわかった気がした。
「素晴らしいお考えです。だが戦場には、いささか勿体ないお言葉ですね。」
「ハハハッ、そうだと思うよ。実際、それを成し遂げられたのはほんの数回だけだ。」
そこまで聞き終えて、少佐の言葉を頭の中で噛んでいたボリスがゆっくりと反論を開始する。
「しかし」
二人の視線が一気に集まる。ボリスは少々こっぱずかしくなったが、反論を続ける。
「しかし、どうしても戦わなきゃならない相手だっているでしょうに。」
「そのときは殺し合いだな。そこの分別がつかない程、私は理想論者ではないよ。」
「線引きが分かりませんな…。」
「助けられそうなら助ける。ダメなら諦める。そんなに難しいことじゃあないさ。」
「なるほど」
意外に淡白だな、と思いながらグラスに口を付けたところで、ボリスはグラスが空になっていることに気づいた。
それに気づいたヒッグスがおかわりを尋ねようとした、その時だった。
ラウンジの中を耳をつんざくような警報が満たした。
「警告、警告、両軍に通達。公国軍の艦隊、Bブロックにて捕捉。高度+10、方位204、距離40000。艦数からリージョン艦隊と推測。現在は一定の速度で49号宙域方向より侵入中。
発進可能な機体は全機スクランブル、艦隊をインターセプトせよ。
既に展開中の部隊にあっては、Bブロックに集結し、防衛体勢を整えろ。これは訓練ではない。繰り返す、これは訓練ではない。」







コメント